黒猫館殺人事件 …執筆の背景
今、一人の男が宿の部屋の中心まで机を動かしてきて、そこに紙束をドサリと積み上げ、万年筆を平行に並べ…
その正面に、腕組みして、足を組んで、椅子の背もたれに寄りかかっていた。
彼の正面には、日が差し込んでくる窓がある。
その光は、まるでスポットライトのように机をちょうど照らしだし、ハタから見れば軽く劇場の舞台のようでもあった。
……だが、それは同時に日差しの暖かさを机の周りに運んでくるようなもので。 椅子にもたれる男を心地よい眠りへといざなうのであった……
- 「ホラ! ま〜た寝てるッ!!!」
男を、眠りから首根っこ引っ張ってくるような、すっとんきょうにも聞こえる少年の声が響いた。
「もう! 少しは危機感とか緊張感とか、もってはもらえないんですか!?
ボーマンさんだけなんですよ、何も書けてないのッ!!」
事情はこうだ。
光の勇者一行は、武器やら防具やらを穴場「フェイクギャラリー」にて新調し、あまつさえマジカルラスプまで買っちゃったもんだから金欠地獄街道真っしぐら。
そこでリーダーのクロードが打ち立てたプランはといえば。
「出版して印税を少しでも!」
バトルで荒稼ぎしている間にも印税による収入が入ってくるという、効率を考えてのことだった。
みんな、最低でも1冊仕上げることができるくらいだった。
ところが。 文才も執筆レベルもあるこの男、ボーマンだけが1冊もあげられずにいたのだ。
別に失敗続き、というワケではない。 何も書いていないのだ。
「あのな、お前らが早く書き終わらせてるだけなの。 俺が書いてるのはサスペンス!
トリックのプロセスとか色々考えてんだよ。 一発屋な本出しても、収入なんか出やしねぇだろ?」
「そんなこと言って、何も書けてないじゃないですかっ。」
「トリックの連鎖。 その組み立てはもうできた。
登場人物の位置関係、動機と仕掛けの連鎖も、うまいこといってる。
誰をどうするのかも、もうおおよその筋書きはできてる。 ただ……描写に問題があってなぁ。」
描写とは、人物の感情表現や事態を文に描きだすことを言う。 文才がありながら、描写がしにくいとでも言うのだろうか。
「…何の描写ですか?」
クロードは念のために聞いてみた。
「サスペンスにはつき物の……襲撃、殺害の瞬間。
瞬間がダメなら、せめて死体の描写を…と思ってるんだが、ど〜にもイメージがなぁ…。」
「トリックや動機までできてるんなら、そんなの簡単じゃないんですか?」
「そう思うだろ? 俺もそう思ってたんだが…いったん考えて読み返してみたら、これがまたチャチなモノでさぁ。」
そう言って、ボーマンは紙束の隣に乱雑に散らばっているメモを1枚とり、それをクロードに見せた。
「2人目の犠牲が出るとこを描いておいたんだ。見てみ。
この犠牲者は、犯人の妻と妹とに二股かけた上に、紙くずみたいに簡単に捨て…二人を追い詰めた。
他の殺人は、こいつを殺す動機を覆い隠すためのついでに殺したようなもんだから、
ここの描写がカナメになると思っていい。」
人物の背景を聞いたうえで読んでみると、確かにクロードも違和感を感じた。
- ナイフを握り締め、にじり寄ってくる黒猫。
らんらんと光る黒猫の瞳孔は底が見えないくらい、昏く、深い闇で。
闇に意識を引き込まれた瞬間、男は切り裂かれた。
「……なんだろう。 確かに、なんか入ってきませんねぇ。」
クロードはいいながらメモをもう一度読み返した。
「もしかして、他のもこんな感じの描写なんですか?」
「いや? ここまで何も書けないのは、この部分だけだ。」
ボーマンは適当なメモを取り出し、クロードに手渡した。
そこには謎解きする主人公が、黒猫と対峙するシーンがびっちりと書かれていた。
- 後ろに向かって倒れこんだリートに、黒猫は真正面から飛び掛って、
にぶく血の色を照り返す短剣を突き立ててきた。
恐怖による無意識か、とっさにリートは身体を真横へと転がし、黒猫の一撃をかわした。
ナイフは床の木目に挟まり、抜けなくなったスキを狙って………
「…さっきのメモとはものすごい違いですね。 でも、臨場感は感じます。」
「だろ? ここはなんかさ、いっつもこんな状況に追い込まれてるから、ささっと書けたんだがよ。
なんていうか、殺意を持ってどうのこうの…ってのは……なんかピンとこねぇんだ。」
ぼーんやりとした様子でそう言い、ボーマンは何気なく、テーブルの上にあったフルーツバスケット…に、備え付けてある果物ナイフを手にとった。
「このナイフ一点に殺意を込めて……いや、恨みの念を込めて? …それじゃ動機バレるか。」
あとは画竜点睛の点を描くのみ、といったところのようだ。
それだけに、クロードもウーンとうなりだした。
一時の沈黙が、二人と、二人がいる部屋を支配した。
唯一の音があるとすれば、ボーマンの、ぴたぴたと果物ナイフを指でもてあそぶ音くらいだろうか。
二人は、しばらく何も言わずにいた。
- 「あ、てッ!」
不意にボーマンが声をあげた。
手元が狂ったのだろうか…彼の指から血が出ていた。
「ちょっと、気をつけてくださいよ…。」
ボーマンの声にびっくりしたクロードが、ちょっと不安そうな顔をしてこちらを見てきた。
「ん、悪ぃ悪ぃ。」
そう言いながらボーマンが、指からにじみ出てくる血の珠を口に含む。
……その時、何かが一気に頭の中を駆け抜けたような気がした。
モヤついていた糸が、たちどころにまっすぐな直線を、ピンッと描くような。
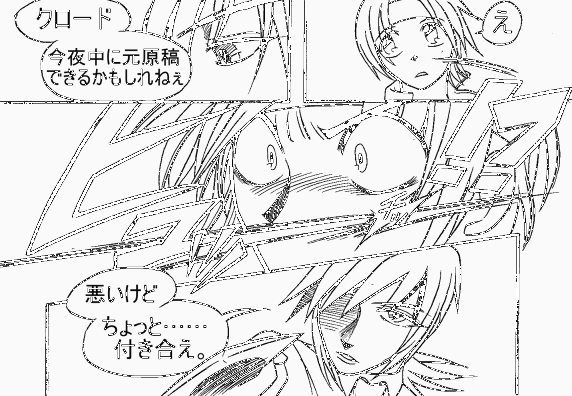
いきなり、クロードは果物ナイフで頬を浅く切られた。
「!!! な、んですかいきなり!!」
唐突なことだけに、クロードの動悸は早まり、頭の中は多少の混乱によって整理がついていなかった。
体の熱が一気に顔に集中してくるような気がした。そしてその熱が、なおさら頭の整理をつかなくさせていた。
真正面では、ボーマンが果物ナイフを逆手に持ち替えて、クロードに斬りかかってきた。
「ちょッ、危ない!!」
あいにくと、剣は当然ながら自分の部屋に置いてきている。
そのためクロードは、的確にボーマンの手首を狙って、ナイフの一撃を払っていた。
剣こそないが、クロードは戦闘態勢をとり、ボーマンの目を見て次の出方を伺っていた。
ボーマンはといえば、どこか神懸かったような、ぼんやりとした雰囲気を漂わせ…
くるっと手の中でまわしたナイフの切っ先一点を見つめながら、その切っ先をクロードへと向ける。
「……一応、この殺される男はインテリなんだけど……でもまぁ、どうにかなりそうだ。」
「はい!?」
叫びながら、クロードはそばにあったソファへと転がり込んだ。
クロードが「は」の字を言ったのと同じタイミングで、ボーマンがナイフを逆手に持ち直して襲い掛かってきたのだ。
仲間に、理由もなく、唐突にナイフを以って襲われるという恐怖。理不尽さ。
クロードはパニックになるところを、必死になって冷静さを保って、ボーマンの目とナイフとを交互に見ていた。
皮肉にも、その恐怖と理不尽さが、彼に冷静さを保たせていた。
「…なんでこんなことを、う、わぁ!!?」
もっぱら問いかけるのはクロードばかりで、ボーマンは、ただ無言のままナイフをドッ、ドッとクロードがいた場所に突き立ててゆく。
クロードは、かろうじてそれを寸での所で回避していた。
「やめてくださいボーマンさん!」
月並みなセリフしか出てこなかったが、気の利いたセリフを吐けるほどの余裕なんてありはしない。
ベッドの中にあった羽が数枚、マクラの綿くずと一緒に舞い上がり、クロードの呼吸はどんどん早まっていった。
ギリギリのところでナイフをかいくぐっていたが…クロードは舞い上がった羽が目に入りかけ、一瞬ひるんでしまった。
そのスキに、一気にソファへ押し倒され、仰向けになったクロードの上に、ボーマンがまたがってきた。
「!!!」
肩をがっちり鷲づかみにされ、そのままぐっと強くソファに押し付けられた状態で、クロードはボーマンのナイフを見つめていた。
心臓は極限までドッドッドッと大きく響き、全身を振動させるかと錯覚させた。
- (殺される…!)
確実にそう思った。
そして、ボーマンのナイフがクロードの額めがけて、一気に振り下ろされる!!!
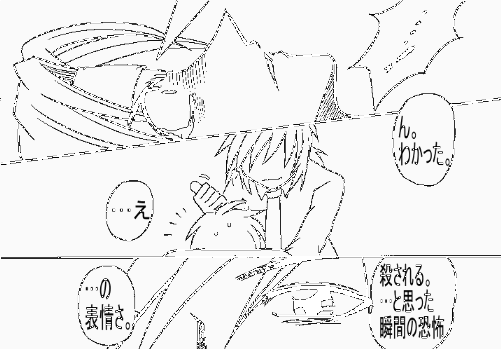
「…どういうことですか…?」
何を思ったのか、ボーマンはクロードのバンダナから数ミリというスレスレのところで、ナイフの切っ先を止めたのだ。
「言ったろ。 描写がいまいちピンとこねぇって。」
「……もしかして、僕でイメージ膨らまそうとしてたんですか!?」
「ああ。」
「殺人モノの!!?」
「サスペンスと言ってくれぃ。」
クロードには信じがたい話であった。
読み物を作るために、そのイメージを膨らませるために、わざわざホンモノのナイフで自分に襲い掛かってきた。
自分は、本気で殺されるかと思ったのに、フタをとってみればイメージを膨らませるためだけ。
クロードは、冗談ではない…と、怒鳴りつけてやりたかったのだが、よく考えてみれば、彼がイメージを膨らませようとしたのは出版のためであって、
そしてそれを頼んだのは、ほかならぬ自分であって。
そう考えると、クロードは怒鳴るに怒鳴れなかった。
「さてと。それじゃさっそく書くとしますかぁ。」
ボーマンはナイフをバスケットに戻して、机に向かいなおした。
「2時間くらいしたら、編集とか校正作業してくれねぇか。
同時進行でやろう。その方が効率いいだろ。」
ボーマンは、まるで何事もなかったかのごとく、机に向かって万年筆を手にとっていた。
まるで、たった今行われた生きるか死ぬかの恐怖のやりとりなど、なかったかのように。
クロードはしばらくの間、呆然とその場にへたり込み続けていた。
後日――――……
ボーマンが打ち出した「黒猫館殺人事件」が、ベストセラーとなったらしく、印税がどっと入ってくるようになった。
「すっごぉいボーマンさん! 待たせただけのことはあるわね!」
「これで金欠地獄脱出よーぉ! おつりが来るわぁ!」
お風呂だってめったに入れないような生活だったため、女性人が一気にわいた。
「でもこの作品、ほんっとうによく描けてますわよね。
特にこの2人目が殺されてしまうトコ! 背筋がぞくぞくしましたわぁ。」
セリーヌにそう言われた時、クロードはボーマンが胸の上に馬乗りになってきた瞬間を思い返した。
「ですよねぇ。ココだけものすごく怖くて、引き込まれちゃいましたよね。」
おそらく、読み手だけではなく…そのワンシーンは書き手さえも魅入らせ、引き込んでしまったのかもしれない。
クロードはそう考えて、一人寒気を感じていた。